- 6月 24, 2025
- 7月 25, 2025
夏の養生と漢方
さて、夏の養生についての解説です。季節の養生シリーズとして、秋、冬、春+梅雨とやってきましたが、やっと一周して夏の解説になります。夏の養生はとても大切なので、かなり長くなってしまいました。どうかご容赦ください。
夏バテ
夏に体調を崩すと、いわゆる「夏バテ」と言われます。東洋医学的には夏バテの事を「注夏病」と言ったりします。しかし、夏バテって、いったいどんな病態なのでしょうか。
これは実に多彩な病態があります。暑い所の仕事で脱水になり熱中症・熱射病となってしまう方をはじめ、食欲低下で動けない、寝不足(暑くて)でだるい、自律神経の乱れからめまい、吐き気、体温調節の機能低下、また、冷房で冷えて腰痛などを起こすこともあります。
巷でも言われているように、この数年の気候は暑さの度合いが昔とは変わってきております。夏とは別の酷暑というべき季節が加わってしまったようです。
しかも日本は湿度が高く、気化熱による体温の発散が難しい環境になっています。このような「日本の夏」に、どのように対応したらよいのでしょうか?
東洋医学からみた夏
東洋医学的には、五臓でいうところの 「心」 に負荷がかかりやすい時節と言われます。「心」 というのはいわゆる臓器としての「心臓」だけではなく、血の巡りである「循環」を意味します。汗や水の摂取量が多くなり、ポンプを中心とした循環システムに負担がかかるという事です。また、心は精神的な活動、意識、感情、思考などをコントロールする働きもあります。
「心」が乱れると、「心」が養う「脾」と言われる消化機能にも影響が出ます。つまり、汗と水分摂取などの水の出入りの調節能力が追い付かず、体の循環が乱れ、元気がなくなり(精神的な活動性が低くなり)、徐々に消化能力の低下から食欲もなくなり…というドミノ倒しになりがちです。

また、エアコンを使用することで、夏なのに冷えてしまうクーラー病と言われる病態も見られます。暑さと冷えの寒暖差がやはり体力を奪い、自律神経の乱れを助長します。サーキュラー(扇風機など)を上手に使いながら、エアコンの設置温度をこまめに調節するなど、部屋の適切な温度をキープできるとよいのですが、機械自体もこの激しい暑さのためか、もう能力限界を超えてしまい、調節機能が乱れ、エアコンも夏バテしているようにも思います。
夏の養生
では具体的な対応策について考えてゆきたいと思います。一般的な夏のイメージとして、夏には冷たい麦茶をカーっと飲んで、さらっと入るソーメンなどおなかに優しいものを食べ、クーラーの効いた部屋で涼んでくつろぐ、というのが安直なイメージ(?)ですが…、これが意外に体の負担になることがあります。
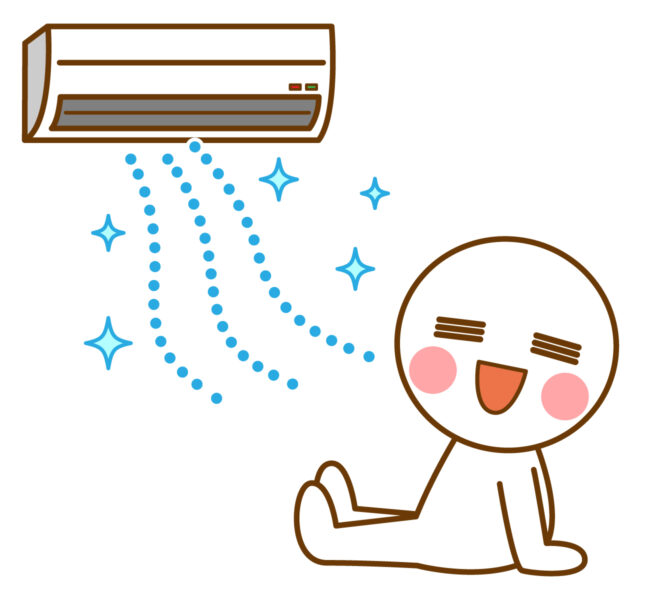
まずは 「冷たい水分」 です。量が多いとおなかが冷えてしまい、消化機能が低下することがあります。夏と言えば、「氷の浮いた冷たい麦茶」というイメージがありますが、飲み過ぎると確実に、「物理的に」 おなかを 「内側から」 冷やします。冷えれば、なんとなく良いような気がしますが、コップ一杯ならまだしも2杯も3杯も飲んで、ついでにアイスクリームも入ると、ご本人はなんとなく涼しくなりますが、おなかは冷えすぎて非常事態になっている可能性があります。何とか冷えた消化管を温めようと、体内での熱産生を促し、より暑く、より体力を消費してしまうことになります。
汗をかいた分だけ、しっかり水分補給をすることはもちろん大切です。しかし冷たすぎるものは、かえって体の負担になります。一見すると変な話ですが、「暑いときには熱いお茶がいい」といわれます。体が内側から温められると、体の外側も暑いので、体としては緊急に体を冷やさねば!と反応して、消化管は温まるし、体は体温を下げようと働くので、ゆっくりですが体が楽になります。たくさん飲む必要はありませんが、湯のみで軽く一杯飲むだけでも実感できることがあります。適度に水分補給をした後に、暑いお茶! 試したことがない方は、暑いときの熱いお茶を是非一度お試しください。

※ 念のため、熱いお茶での火傷にはご注意ください。

また、夏の定番であり、食欲低下の対策にはもってこいの 「そうめん」 ですが、意外に含まれるビタミン、ミネラルは少ないのです。、汗や運動でで失われた栄養素は、別に摂取する必要があります。カリウムや適度な塩分、カルシウム、ビタミンBなどを含む食品を摂ると良いといわれます。豚肉や夏野菜などはこれらを含みますので、是非ソーメンなど度一緒に、副菜、薬味として積極的にとるようにお勧めします。ミョウガには発汗作用や血行促進、食欲増進などの効果があり、きゅうり、スイカ、トマト、ナス、冬瓜(冬とありますが夏の野菜です)などの夏野菜は水分の代謝を改善し、体をやんわりと冷やしてくれるといわれています。
そして近代文明の英知である 「エアコン」 ですが、最初に書いた通り、体を冷やし過ぎてしまうことがあります。外気温との差があると、冷えたり熱くなったりで、体の調節機能が温度差に悲鳴を上げてしまいます。最近の気候はエアコンなしではとても乗り切れませんが、本末転倒のようですがエアコンを使用しながら衣類を細かく調節して、体が冷えすぎないように調節することが大切です。
また、過度な運動は熱中症などの原因となりますが、日々、ぐたーっとゴロゴロ過ごすのも考え物です。適度な、そして習慣的な発汗が大切で、梅雨の養生でも少し書きましたが、春から初夏にかけて、「汗をかく練習」が重要と言われます。冬の間に汗をかく機能が低下しているため、あえて(適度な)運動や入浴などで発汗する習慣をつけることで、暑さへの対応力が鍛えられ、体の全体的な新陳代謝を促し、自律神経の乱れを改善します。もちろん運動の際は無理せず、適度な範囲と軽い発汗にとどめて、水分補給も忘れずにお願いします。

夏の寝不足
寝不足も夏バテの原因です。枕草子で 「夏は夜」 と言いますが、当時の夏の夜はそれなりに風情があったかもしれません。しかし、最近の夏の夜は熱帯夜が続き、夜間でも外気を締め切ってエアコン稼働が必須となりつつあります。湿度も気温も高く、お住いの環境にもよりますが、エアコンを使わなければ寝苦しくて寝不足、使ったら使ったで極度に冷えてしまい倦怠感が強くなってしまうこともあります。何とか快適な環境にしようとエアコンのタイマー設定や、扇風機なども駆使して、少しでも快適な睡眠をとれるよう、日々いろいろと努力されていることと思います。
しかし、それゆえといいますか、快眠のための 「室温調節」 自体に手間がかかってしまいがちです。時間的な長さとしては十分に睡眠をとっていても、夜中にエアコンの操作をしたり、掛け物の調節をしたりすることで、いったん睡眠が途切れてしまい睡眠の質が落ちて、結果的に疲労がたまってしまうこともあります。

極論ですが、ご自宅や気候(気温、湿度)の状況により環境の調節がなかなか難しいときには、やはりエアコンを一晩中稼働させて、掛け物と衣類の調節でしっかり眠るという選択が良い場合もあります。電気代も高くなり、節電や、エアコン自体が得意でない方もいらっしゃると思いますが、体調を崩せばそれ以上に損益が出てしまうことも考えられます。
また、いろいろと対策をとっても、どうしても眠れなかったり、体調の悪くなってしまう場合は、次の章に書くように、ほてりやイライラをいくらか抑える漢方もありますので、ご検討をいただければと思います。
夏の漢方
それでは最後になりますが、以下に、夏の漢方薬として有名なものをいくつか紹介します。
いわゆる夏バテに「生脈散(しょうみゃくさん)」や「五苓散」、「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」、「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」などが有効です。クーラー病に「五積散(ごしゃくさん)」、食あたり、食べ過ぎ、嘔吐下痢に「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」、「胃苓湯(いれいとう)」などがあります。もちろん病態により、さらに多くの薬があるため、体質や病状を診ながら処方を決定してゆきます。以下に少し詳しい解説を載せてみます。
「生脈散(しょうみゃくさん)」
人参、麦門冬、五味子という三つの生薬のみで構成される薬です。保険収載されておらず、薬局などで購入できる市販薬になります。滋養強壮と体内の潤いを保ち、弱くなった脈を生き生きさせるという意味合いの処方です。初期の夏バテの際に良く服用されます。
「五苓散(ごれいさん)」
おなじみの、どこにでも登場する五苓散です。いろいろな作用を持っていますが、水の代謝、バランスを改善する薬です。吐き気や下痢、むくみ、めまいなどにも効果を発揮します。軽度の熱中症、脱水、水の飲み過ぎにも効果を発揮するマルチな薬です。お子様の夏場の吐き気、下痢にも効果があります。
「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」
補中益気湯という体力低下に用いられる薬がありますが、その夏バテ用アレンジというべき薬です。虚証(痩せ気味で倦怠感の強い方)の方によく処方します。暑さで体調を崩し、食欲低下しているようなときにお勧めします。少し長め(1週間以上)に使用していただく漢方です。
「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」
体を冷やしつつ、汗を押さえて、体の水分を保持する薬です。のどの渇きがあり、ほてるとき、いわゆる熱中症のなりかけの時に処方します。かゆみなどに処方されることもあります。やや実証(体力のある方)の薬のため、食欲や体力が少ない方は、かえって体調が悪くなることもありますのでご注意ください。特に長期に服用すると副作用も出ることがありますので、1週間以上など服用するときは注意してください。
「五積散(ごしゃくさん)」
16種類の生薬を含み、冷えを持つ方のいろいろな症状を改善します。胃腸炎から腰痛まで更年期障害にも効果がみられます。症状があまり強くなく、夏場にエアコンで冷えたり、寒暖差で色々な不調が出ている場合などに良いとされています。
「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」
嘔吐症や下痢症に使用されます。夏場に限ったことではありませんが、おなかがゴロゴロして、嘔吐と下痢が合う場合などは短期に服用いただき、五苓散と併用することもよくあります。
「胃苓湯(いれいとう)」
平胃散という漢方と 五苓散を合わせた漢方です。冷え腹、腹痛、急性胃腸炎、暑気あたり、食あたりなどに効果を発揮します。自分自身でも胃もたれや、食べ合わせ等でむかつきがひどいときなど時々服用します。
「藿香正気散(かっこうしょうきさん)」
こちらも保険収載されておらず、市販されている漢方薬になります。胃腸がもともと弱い方、冷房などにより体調がくずれやすい方、いわゆる夏かぜ、夏の暑いときに冷たいものを摂りすぎて、胃腸が冷やされて下痢・食欲不振・全身倦怠などに効果を発揮します。名前にもある「藿香」とはいわゆるハーブのパチョリを乾燥させた生薬で、独特な香りがあります。
以上、夏場によく使用される漢方薬を紹介してみました。
夏は気分も気温も上がりがちな季節ですが、高温多湿の気候の中で、体への負担も増える季節です。副作用が少ないといわれる漢方と言えど、一種の薬になりますので、飲まないに越したことはありません。日々の生活の中でできるだけ体調を崩さないようこまめに気を使い、養生を心掛け、楽しい夏をお過ごしください。
それでも、もし体調が悪い際や、気になる症状があるときには、遠慮なくご相談ください。

