- 4月 1, 2025
- 6月 3, 2025
ストレスの漢方
今回は、ストレスの漢方と、東洋医学的な解説になります。
ストレスに対しての「治療」という事自体、意外に思われるかもしれません。普段の日常生活の中で、ストレスを感じることも多いと思いますが、時代や社会構造とともに、ストレスの大きさや性質も変わってきているようです。日本は世界的にも治安が良く、安全で、モラル的にも決して低い国ではないと思いますが、それでも生活の中で色々なストレスもあり、生命を脅かすようなストレスは少ないにしても、ハラスメントやいじめ、いびつな人間関係などがニュースをにぎわせているのをよく耳にします。今回はそんなストレスに用いられる漢方と、東洋医学的な考え方をお伝えできればと思います。
大袈裟かもしれませんが、「ストレス」は、特に現代社会においては、誰しも逃れられない人生の問題のひとつです。特にこの記事を書いている3月から5月の期間は、日本においては仕事の入退社、異動、学校の卒業、入学、引っ越しなどが多い時節です。気候的には春の陽気で気分が高揚してくる季節ではありますが、環境の変化も大きくなることがあり、ストレスも大きくなりがちな季節でもあります。
ストレスとは?
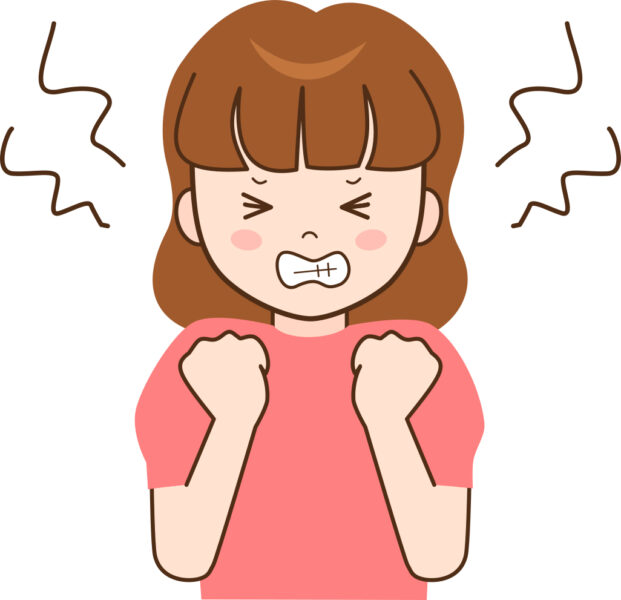
強めに言い切ってしまいますが、生きてゆく上で、ストレスのない人生というのはありません。ある意味、生きとし生けるものすべての生命に、生存競争、環境、外敵などへのストレスがあります。脳を持たない植物にさえ、ストレスに対する反応や、防御機構があるといいます。人類に限って言えば、人間関係などの社会的なストレス、情報過多によるストレス、家族、金銭、自分自身によるストレスもあると思います。老若男女、ストレスの大小、それにご自身で対処できるかどうかの違いはありますが、ほぼすべての人が様々なストレスを抱え、無意識かもしれませんが日々戦っているはずです。一見したところ全くストレスがないように生きていらっしゃる方もいるかもしれませんが、それでも人には言えない、なかなか思い通りにいかないことが、それなりにあるのが人生と思います。(偉そうにスミマセン)
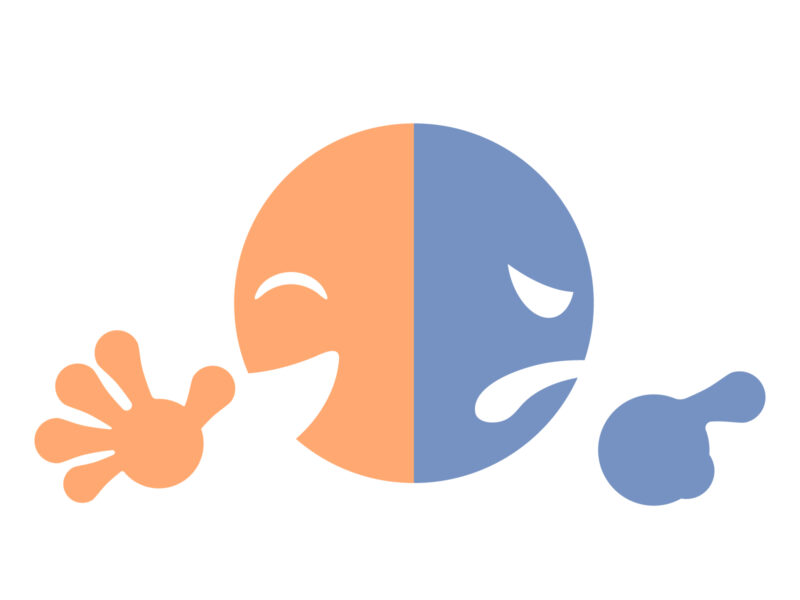
ストレスから身を守るために、一般的に言われる具体的な対処方法がいくつかあります。例えば、ストレス自体から距離を置く、乗り越えるよう頑張る、運動、とりあえず何かを壊す(できれば壊してよいもの)、おなか一杯にする、自身の生活習慣(健康状態)の改善、何か楽しいことをする(気分転換)、瞑想、甘いものを食べる、信頼できる人に相談するなどでしょうか。ちょっと不適切な方法も混じっていますが、いずれにせよ、ご自身の力で「適切に」乗り越えられるようであれば、それはある意味「良いストレス」と言ってもよいかもしれません。
ただ、これらの解決方法では効果がみられないような、ご自身で対処が難しいほどの大きなストレスの場合には、カウンセリングや、内服薬などの対応も必要になることがあります。心療内科、精神科で使用される、いわゆる安定剤、入眠導入剤などもあります。しかし、これらの薬を服用することに対して、心理的な抵抗をお持ちの方も多いと思います。そのような時に、当院ではまず漢方薬の使用をご提案して、それでも不十分な場合には、西洋薬と漢方薬の併用という形での治療をお勧めしております。
ストレスに対する漢方薬
今回の主題でもある、メンタルストレスに使用される漢方について、いくつかご紹介したいと思います。以前のブログ記事で紹介したものと重なる部分はありますが、よりストレスに特化する形で解説してゆきたいと思います。あくまで教科書的な使用方法であり、実際の診療ではこの限りではなく、個人個人の反応の出方や、ストレスの種類によりできるだけ体に合った薬を処方、併用してゆきます。含まれる生薬を考えながら、病状の変化により、その都度、処方を変えてゆきますし、処方や症状で短期間集中的な使用や、もしくは数か月と言った長期間の使用などの判断をします。もちろん症状が改善したら、できるだけ減量、中止を考えてゆきます。
抑肝散(よくかんさん) ・・・怒りはなしや?と問うべし
とにもかくにも、「怒り」があるときに使用されます。丁寧に問診をしないと、本人でも意識していない怒りがあることがあります。理屈では説明できないような怒り、言葉にできないような怒りに効果的といわれます。例えば目つきが鋭く、目が三角になっているといわれるような状態、眉間にしわが出ているような状態です。ちょっとしたことで必要以上に言葉を荒げてしまうような状態によいとされています。ストレスに対して激しく抵抗しているとき、暴力的になってしまうようなとき、例えば体の痛みが強くて、イライラして、近くの方に当たってしまうようなときにも良いと思います。処方のニュアンスは少し変わりますが、胃腸の弱い方は、副作用として胃腸障害が出ることがあるので、胃腸薬の生薬を加えた「抑肝散陳皮半夏」という処方も良いかと思います。

柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) ・・・ 焦り、焦燥感、悪夢に
この処方はストレスに対して恐怖感や、焦燥感、焦りなどがみられるときに良いといわれます。締め切りやノルマに追われたり、得体の知れないプレッシャーに押しつぶされるような感覚、多夢と言って夢を頻繁に見たり、特に悪夢、追いかけられるような夢を見るときには、この処方が良いといわれます。竜骨牡蛎を使用したもう一つの処方に、「桂枝加竜骨牡蛎湯」があります。これは体が(胃腸が)弱い人のための柴胡加竜骨牡蠣湯という考え方もありますが、ストレスに対して対応しきれずに、恐怖感とともに、絶望、落ち込み、ふさぎ込んでしまうようなときに使用するとよいようです。

加味逍遙散(かみしょうようさん) ・・・イライラ、のぼせ、症状の多い方
ご婦人のストレスに使用される代表ともいうべき処方です。もちろん男性にも処方されることがあります。月経に伴うストレス、イライラ、ヒステリー、のぼせ、ホットフラッシュなどがある状態に、まず最初に使用するようなイメージです。ただ、この処方の名前でもある「逍遥」という言葉、これは「揺れ動く、散歩をする」という意味があります。作家の名前でも有名な言葉ですが、もともとある「逍遥散」という処方に、山梔子と牡丹皮という生薬を加えた(加味した)ものが加味逍遙散になります。イライラが多方面に向かい、症状が揺れ動くという意味もあるようです。いろいろなことが気になり、訴える症状が毎回違うようなときに良いといわれます。また、怒っているわけではないけど、お話の際にちくちくと言葉がきつくなるようなとき、また、あるお医者さんの話では、受診の際に一度診察を終えて部屋を出たけど、もう一度戻っていらしゃって、ほかの症状について相談されるようなときに使用するとよい、と表現される先生もあるようです。

加味帰脾湯(かみきひとう) ・・・虚弱体質で不安が強い方
加味逍遙散と同じく「加味」という言葉が使用されていますが、この処方では帰脾湯に山梔子と柴胡という生薬を追加した(加味した)処方になります。ストレスなどから不安や不眠という症状があるものの、かなり胃腸の力が弱く(脾虚)上記のような処方が使いにくいときの選択肢になります。イメージとしてはやせ型でやや声が小さく、体力がなくて胃もたれ、下痢の傾向があり、常に不安なことがあり、たとえ不安がなくなっても、不安がないことが不安というような、次から次へと不安と心配があふれてくるような方に良いと思います。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) ・・・まじめな方、こだわりの強い方
のどの違和感(ヒステリー球などとも表現されます)に対して使用される漢方として有名ですが、その原因はストレスが大きいと言われています。嚥下運動に関わる筋肉収縮と、その運動の調和が乱れている状態で、過度のストレスから筋肉運動のバランス、コントロールの失調をきたす状態と考えられます。使用される生薬の厚朴とは、朴の木(ほうのき)の樹皮になります。朴の木はその大きな葉が朴葉焼(ほうばやき)などに使用され、香りが良いことと、殺菌作用なども持ち合わせ、食品を包むのに使用されることでも知られています。執着をとる漢方とも言われて、延々と繰り返してしまう思考の袋小路や、一つの不安にとらわれて、些細なことや同じことでずっと悩んでいるような状態によいようです。細かくメモを取ったり、比較的真面目な性格の方、もっと言えば〇〇真面目な人にも良いといわれます。

大柴胡湯(だいさいことう) ・・・おなかの張りが強い方、高血圧、のぼせのある方
緊張が強く上腹部の張った感じや便秘がちの方に良い処方です。体格が良くて胃腸炎、胆嚢炎、肩こり、耳鳴りなどをお持ちで、胃酸過多、悪心嘔吐などの消化器症状、高血圧などのある方に良いといわれます。ややのぼせ気味で赤ら顔、イライラ感が出ている方もよい適応です。
黄連解毒湯(黄連解毒湯) ・・・ 胃炎などの消化器症状、目の充血、ほてり、不安、不眠
顔ののぼせが強く、赤ら顔、イライラが強い方の処方です。そういった意味では大柴胡湯とも似ている部分がありますが、こちらはかゆみ症状があったり、不安や不眠がみられる方、目の充血や皮膚症状が目立つ方に効果を発揮する印象です。下剤の力も持っており、下痢しがちな方は注意が必要です。味は苦みが強く、この苦みがイライラや腹部消化管の炎症、不快感などを止める力を持っています。
四逆散(しぎゃくさん) ・・・筋緊張の強い方、隠れストレス、手足の冷たさ
緊張状態が続き、特に腹部の筋肉がガチガチに張っているような方に使用します。訴えとして言葉でストレスをあまり訴えていなくても、この腹部の筋緊張症状がみられる方の多くに、隠れたストレス、他人に言えないストレスを抱えている方がおられます。緊張状態が強すぎて、自律神経失調をおこして手足の冷感を感じることがあります。ストレスで末梢の血管が収縮して冷えていたり、神経的な知覚異常で、手足はまぁまぁ暖かいのに本人は冷たく感じることもあるようです。ストレスと筋肉の緊張をとりつつ、東洋医学でいうところの「気」を巡らせて症状を緩和します。
温経湯(うんけいとう) ・・・月経に伴う症状、冷えとほてり、肌荒れのある方。
温経の「経」はいわゆる血管で、血管を温める漢方と言ってもよい薬です。ただ、自律神経失調のような状態で、下半身の冷えが強いものの、しかし手足や指が時に火照ったり冷たくなったりする方、更年期障害、または不安、不眠のある方で、手足の皮膚の湿疹、しもやけがみられる方に処方することがあります。ストレスとは直接関係しないものの四肢抹消を温める当帰四逆加呉茱萸生姜湯(ツムラ38番)という処方がありますが、この処方をしても、さらにほてりや皮膚、口唇の乾燥、生理周期に伴い症状が変化するようなときに使用を検討します。
酸棗仁湯(さんそうにんとう) ・・・体力、精神力の弱っている不眠症に
やや虚弱体質で、不眠症のある方、不安、貧血傾向のある方にはよく処方します。ストレス性の不眠で、体力がある方でも、一時的に体調を崩しているときなどの不眠、強いストレスで精神的に弱っているときの不眠には効果がある印象です。もともと西洋薬の睡眠剤を服用中で、できれば睡眠薬を減らしたいときに、この漢方を併用しながら西洋薬の睡眠剤を減らすことがあります。
香蘇散(こうそさん) ・・・少し気分が沈んで胃腸障害などがあるときに
とてもやさしい薬で、沈んだ気分を少し上げてくれます。劇的な効果はいまいちですが、体力が弱っているとき、くよくよしてしまう時、なんとなく食欲が出ない時に良いようです。この薬が効いた方は手放せなくなる方もいらっしゃるほどです。いわゆる風邪薬の一つではありますが、魚介系の食中毒に使われることもあり、ただの風邪薬にしておくにはもったいない薬です。香附子、蘇葉、陳皮、甘草、生姜という食品に使用されるような生薬から作られており、副作用はほとんどないと考えてよい薬で、ご高齢の方にも比較的に安心して処方できます。
補中益気湯 ・・・気力も食欲も落ちているとき、うつ傾向の時に
補剤と呼ばれる食欲と活力を補う薬のひとつになります。ストレスにより体調を崩し、体力が落ちて、元気がなくて、食欲も落ちているようなときに使用します。少量ですが、柴胡、升麻という生薬が含まれており、気分の落ち込み、緊張の緩和に効果もあります。症状が軽ければ1~2週間などのように短期的に使用することもありますし、長年にわたり症状が続いているときは、治療として同じく数か月~数年にわたり使用することもあります。胃下垂などの内臓下垂の際にも良いといわれます。体力が落ちてじわじわと汗をかいてしまうような多汗症に使用されることもあります。

以上、ストレスに関する代表的な漢方を挙げてみました。特に柴胡という生薬を含む漢方は、ストレス症状に使用されることがあり、今回紹介した漢方以外にもたくさんあります。ただ、やや強めの生薬ともなるため、使用の際は少し注意が必要です。また今回は総論的なお話でしたが、機会があれば、また折を見て症状別などによる詳しい解説をしたいと思います。
何か気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
