- 12月 5, 2024
- 5月 26, 2025
漢方の選び方 その1
漢方の選び方について、数回に分けて書いてゆこうと思います。まずは第1回です。
漢方を処方する際に、「病名漢方」という言葉があります。
ちょっと揶揄を込めた言葉で、漢方を志す者からすると、あまりいい意味とは言えません。簡単に言えば、病名だけで漢方を決めるのはなるべくやめましょうという教訓を含んだ言葉になります。
漢方を選ぶ際に、もちろん主訴(しゅそ:一番強い症状)である苦しい症状が大切なのですが、それだけで処方を決めると、あまり効果が出ないことが多くなります。
主訴からひらめく処方名を一度おいておいて、主訴は関係のない「体質」や「主訴以外の症状」をチェックすることがとても大切です。ここが西洋医学と比較され、一般の医療現場から見ると、とっつきにくい大きな要因でもあります。
例えば、「頭痛」で、頭が痛くて受診したのに、いろいろ診察、検査が終わると、医師から「足のむくみによく効くこの漢方にしましょう」といわれたら、人によっては「えっ?頭痛は?」「なぜ??」となるかもしれません。

解説すると、その言葉の裏には「頭痛に効果的な漢方は数種類(細かく言えば十数種類)あり、その中でむくみを伴う際に効果的なものは、この方剤」という考え方なのですが、途中を端折るとなんだかよくわからない頓珍漢なやり取りになってしまうのです。漢方をよくご存じの方でしたらその辺のことは言わずと知れた部分なのですが、一見関係のない薬が、間接的に効果を発揮することも多いのです。
実際にはその患者さんの病態が、その薬の主な効能に入っていないこともあります。医療用に保険適応もある漢方について、例えば、尿管結石に用いられる芍薬甘草湯などは、適応の実際の文言では、「急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛」という適応になっています。そこに「尿管結石」とは書いてありません。しかし実際に尿管結石の疼痛に対しては非常に効果があります。漢方には昔から伝わる一子相伝的な使い方や、流派によって異なる使い方もあり、いい加減と言われてしまうかもしれませんが、正直、最終的に効く効かないは、使ってみないとわからないこともあります。(もちろん西洋薬でもエビデンスがあったとしても、患者さんによって効果が薄いことは多々あります。)
このように経験的に用いられることもある漢方薬では、その処方と、患者さんの病態、病状が簡単には結び付かないことがあります。医療を提供する側から見ても、その処方を出した理由が(処方内容を見ただけでは)、ほかの医師や、後から見返した際にわかりにくいことも多々あります。
人間の体はその人ごとに体質があります。誤解を恐れずに言えば植物や畑の作物と同じように、いろいろな性質があります。極論ですが、ニンジンを育てるのと、ジャガイモを育てるのでは、季節も肥料も水はけも違ってくるのと同じように、人間もその体質、暑さ寒さや、栄養、水分バランスなどで治療も変わってきます。特に体力がある方に処方する強めの薬を、体力の弱い人に処方したりすれば、寒気(冷え)が強くなったり、吐き気を催したり、治すどころか悪化してしまうこともあります。

体質をしっかりと見極めて、大きく間違えた処方をしないことが大切になります。
漢方で比較的よくみられる副作用は「下痢」になりますが、たくさん食べる方、体力のある方用(実証)の方剤は下剤の成分が含まれていることがあり、人によっては(食の細い方、体力の少ない方は)排便が緩くなることがあります。ただ、これも処方を出す際に説明させて頂くこともあるのですが、ある程度の下痢は、「症状が治る過程」という事があり、腹痛などがなければ一時的な薬の減量などで経過を見ていただくこともあります。
生薬を医院で一から調合する煎じ薬であれば、その人に合わせて下剤成分だけ少なく調合をすることも可能なのですが、一般的なエキス剤では、規格が決まっており、そのさじ加減が難しい場合があります。
ブログ記事 → 煎じ薬とエキス剤
もしご自身で漢方を選ぶ際は、病名や症状だけでなく、できれば体質、少なくとも体力があるか、ないか(実証か虚証か)、だけでも気を付けるとよいと思います。特に体力のある方用の薬は、少し気を付けながら服用をするとよいと思います。
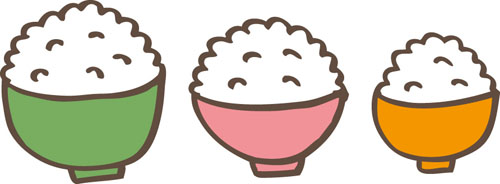
以上、漢方を選ぶ際のちょっとしたコツ その1 でした。
何か気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
